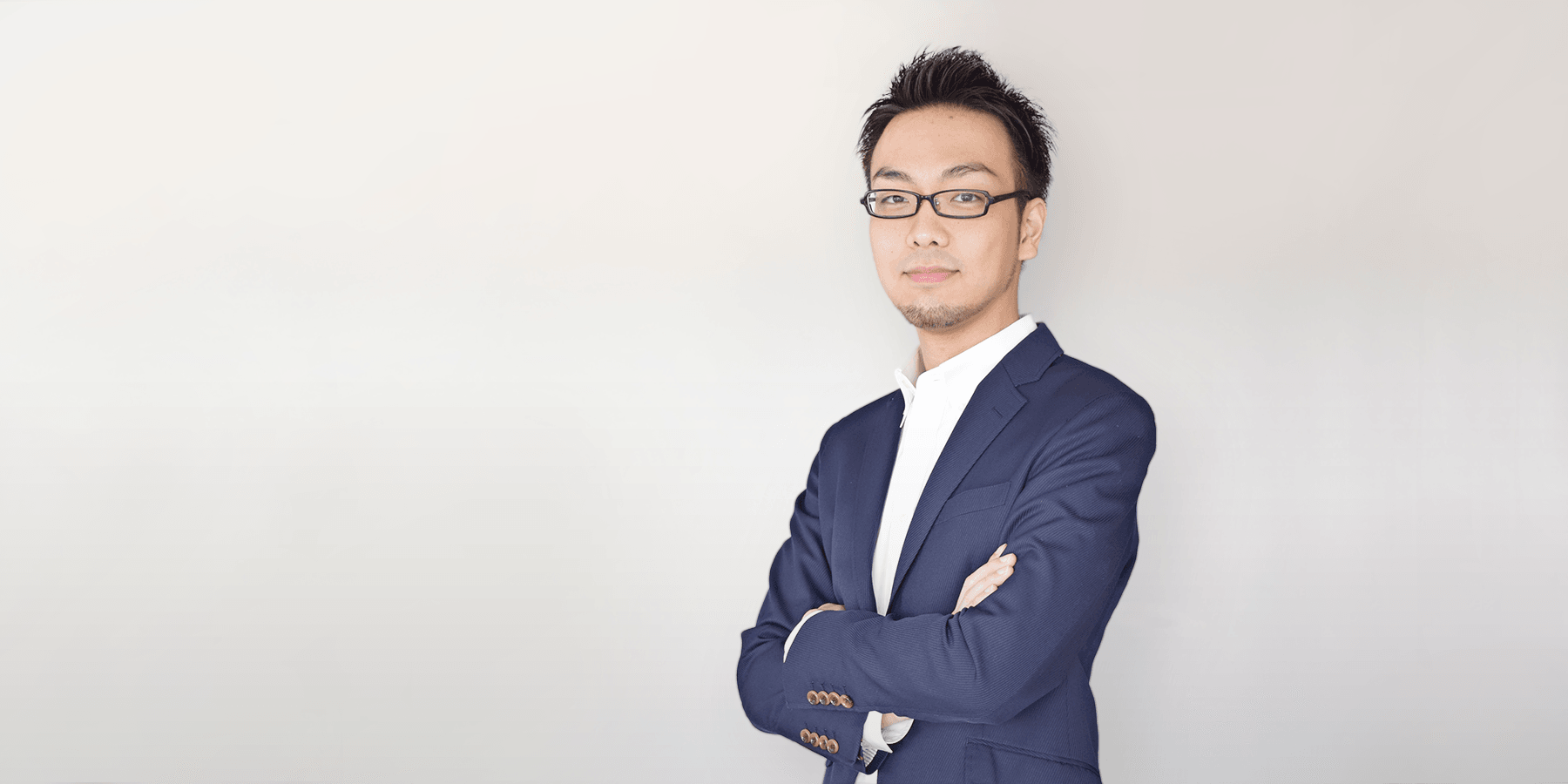

株式会社サイバーエージェント インターネット広告事業本部 エグゼクティブコンサルタント
瓜生 翔
2011年、サイバーエージェントへキャリア入社。 1年半のアカウントプランナー経験を経て、SEMコンサルタントへ転身。 2014年8月、プロフェッショナル職としての最高ランクであるエグゼクティブコンサルタントに昇格。 同年10月、サイバーエージェントグループ総会にてベストプレイヤー賞を受賞。
“場合分け” と “細分化”
SEMに限らず運用型広告というものは、“場合分けの広告である”ということが言えるのではないでしょうか。
「Xという属性を持つユーザーの場合には、aという広告を表示させる」
「Yという商品を購入の場合には、1購入あたりb円までの投資を許容する」
コミュニケーションの最適化を図り、また、投資対効果の最大化を図る上で、運用型広告はこのような“場合分け”で成り立つシステムであると、私は捉えています。
例えば、同じ「転職」という語句で検索をしたユーザーでも、そのユーザーが活動している場所、そのユーザーの年齢や性別、そのユーザーが検索をした曜日、時間帯、デバイスなど、全ての“場合”において、その背景や検索意図、その瞬間のモチベーションは少しずつ異なるはずです。
つまり、SEMにおいては、ユーザーの検索行動に連動した広告を出す以上、それら全ての“場合”に対して、本来最適な広告表現というものが存在し、また、その広告を出稿することに対しての最適な投資金額が存在するはず、ということが言えるのではないでしょうか。
場合分けを行う方法は、基本的には“細分化”です。
“細分化”にも、時間軸における細分化と、コンポーネント(*)軸における細分化があると考えていますが、今回のコラムでは、後者のコンポーネント軸における細分化について、主に述べていきます。
(*)コンポーネント・・・アカウントを構成する要素。具体的には、「キーワード」や「広告グループ」、「キャンペーン」などを指します。
さて、SEMというものに向き合い始めてまだ間もない頃、私にも、「時間と労力さえ無限にあれば、細分化はすればするほど(対効果でサチレーションはしていくにせよ)良い結果を生むものである。」と考えていた時期がありました。
前述の通り、全ての“場合”において、その検索行動の性質というものは厳密には異なるはずなので、それぞれに対して異なるアウトプットが行える状態(即ち配信システム上は、それぞれに対して異なるインプットが行える状態)こそ、細やかで、正しい運用の姿なのだろうと考えていたわけです。
しかしこの考えは、経験を積んでいくにつれ、必ずしも全てのケースに当てはまる正解では無いと、気付かされていくことになります。
理由は大別すると、下記3つとなります。
1:「データ容量」の観点
2:「モニタリング」の観点
3:「統計量」の観点
「データ容量」の観点
1つ目の観点である「データ容量」とは、物理的なアカウントを構成するコンポーネントのボリュームを指しています。
例えば、少し前までは、仮に100万のキーワードで構成されるアカウントで、全てのキーワードに対して、ユーザーの位置する都道府県別にコミュニケーション(広告文)を細分化したいと考えた場合、入稿しなければならないキーワード数は、100万キーワード×47都道府県で、単純計算4,700万キーワードでした。このボリュームで運用をすることも不可能ではありません。不可能ではありませんが、入札調整、広告文やリンク先URLの差し替え、レポーティングのためのデータ集計など、全てのアクションにおいて、この物量がついて回ることとなります。
例えば、データ容量の大きい、処理に非常に時間のかかるExcelデータ・CSVデータを、何十ファイル分も扱うこととなり、またそれを媒体側にデータ送信(入稿)するにも、都度、かなりの時間を要することになる、ということです。(そもそも、Excelを動かすためにもそれなりのハード環境が必要です。)
この状態では、全ての施策、レポーティング、アクションにおいて、相当量の工数と作業時間が発生し、スピーディな運用を行う事は、非常に難易度の高いものとなります。
つまり細分化を行う上で重要なのは、それによって得られる広告効果上のメリットと、オペレーションその他において発生するデメリットとの二律背反を意識し、そもそも細分化による効果がどの程度のものか、それを踏まえ、どの程度まで細分化することが妥当と言えるのか、“判断”をすることである、と言えます。
その結果として、例えば、「配信の●●%を占める、関東1都3県だけ、都道府県別に細分化を行いましょう」といったような着地になるわけです。
ただし一方で、施策を打ち尽くされたアカウントであればあるほど、それ以上の改善を行っていく上で、対効果が決して「大きい」とまでは言えなくても、こうした領域に踏み込んでいかざるを得ないケースがあるのもまた事実です。
(月の配信金額が1億円のアカウントであれば、例えコスト効率化1%の施策でも、100万円分がコスト削減されるわけなので、ある意味当然とも言えます。)
より一層の改善を目指す上で、戦略的にコンポーネントボリュームの増加を許容する。それでいて、運用の“精度”と“スピード”は担保せねばならない。
こうした場合に必要となるのは、圧倒的なリソース(人手)か、インフラ(システム)です。
即ち、大量データの扱いに習熟したオペレーション体制が整えられているか否か。大量キーワードの実績を短時間で集計しアウトプットできるインフラを有しているか否か。こういった点が、運用の精度とスピードの観点で、非常に大きな差になり得るということです。
例え、どんなに優秀な運用者でも、オペレーション体制やインフラ無しに、スキルだけでこの点をクリアすることはできません。勿論、極力データ容量を抑えながら、最大限のパフォーマンスを発揮するといった“工夫”は可能です。しかしながらそれだけでは、運用上、とれる選択肢の幅が狭まってしまうということが言えるのです。
「どこに任せるか?」よりも「誰に任せるか?」と言われるようになった運用型広告の世界ですが、上記のような観点から、「どこの誰に任せるか?」という表現の方が、より適切であると私は感じています。
次回のコラム、後編では、残りの「モニタリング」の観点と、「統計量」の観点についてお伝えしていきます。
-関連記事-
SEMにおける「細分化」と「集約」:2


