「サイバーエージェントクリエイティブDAY」
当社インターネット広告事業本部 クリエイティブ部門にて、様々な領域の第一線で活躍をされている豪華なゲストの方々をお招きしお話をお伺いする社内クリエイター向けイベント「サイバーエージェントクリエイティブDAY」を2025年3月11日(火)に当社 極AIお台場スタジオにて開催いたしました。
第3回目となる今回も、様々な分野から特別なゲストの方々にご登壇いただき、クリエイティブ部門メンバーをはじめ、一部の営業職社員も含めて200名超のメンバーが参加しました。
今後も、テクノロジー、クリエイティブ、エンターテインメントなど幅広い領域で様々なパートナーのみなさまとの取り組みを通して、インターネット広告の新しい価値を生み出す挑戦を続けてまいります。
今回ご登壇いただいた5名のゲストの講演内容を全4編にてお届けします。
ご登壇者様 ※ご登壇順
第1編
石川涼 様(株式会社せーの 代表 「#FR2」創設者)
熱狂こそが、ブランドの価値を決める 〜どこでも買える時代に選ばれるブランド戦略〜
http://www.cyberagent-adagency.com/event/874/
第2編
松村宗亮 様(茶道家 SHUHALLY代表)
茶道から読み解くクリエイティブの本質 〜伝統と革新から生まれる創造力〜
http://www.cyberagent-adagency.com/event/875/
茶道から読み解くクリエイティブの本質 〜伝統と革新から生まれる創造力〜

裏千家茶道準教授
茶道教室SHUHALLY代表
松村 宗亮(まつむら そうりょう)
日本大学文理学部哲学科、イギリス国立ウェールズ大学大学院経営学科卒業。 学生時代のヨーロッパ放浪中に日本人でありながら日本文化を知らないことに気づき、帰国後に茶道を開始。裏千家茶道専門学校を卒業後、”茶の湯をもっと自由に、もっと楽しく” をモットーに横浜や東京にて茶道教室SHUHALLYを主宰。生徒数は100名を超える。 茶の湯の基本を守りつつ現代に合った創意工夫を加えた独自のスタイルを構築し、これまでに海外15カ国、首相公邸などから招かれ多数の茶会をプロデュース。 コンテンポラリーアートや舞踏、ヒューマンビートボックス、漫画等、他ジャンルとのコラボレーションも積極的におこなう。裏千家十六代家元坐忘斎に命名されたオリジナル茶室「文彩庵」はグッドデザイン賞を受賞。
お茶の歴史について
今日は茶道について、特にお茶会に参加する機会の少ない方々に向けてお話しさせていただきます。抹茶は元々中国から伝来したものですが、日本で独自の文化として発展しました。中国では衰退してしまいましたが、日本では抹茶の飲み方と精神性が丁寧に継承され、抹茶の文化は早くから洗練されていきました。そして、茶道の作法や精神性は、武士階級だけでなく、庶民の間にも広く浸透していきました。その中で特に重要な存在が、千利休です。
堺の商人として、彼は外交的な営業努力と卓越した才能によって、茶の湯の世界に進出していきました。当初は目立たない存在でしたが、その創造性と即興的な才能により、徐々に頭角を現し始めます。織田信長の茶の湯の師範として、また豊臣秀吉と共に茶道の発展に大きく貢献しました。宮中でも有名で、金の茶道具を用いて茶会を催し、その影響力を広げていたちがですが、彼の最も重要な功績は、「わび」と「さび」の概念を深く昇華させたことです。これらの美意識は以前から存在していましたが、千利休によって新たな深みと意味を獲得しました。一般的には、質素で洗練された美的感覚を表現するものとして理解されていますが、これが400年の時を経て、現代の世の中にも大きな影響を与え続けているということは、特筆すべきことだと言えるのではないでしょうか。
茶会の設計はクリエイティブの本質に通じている
みなさま、お茶会に参加されたことはありますか?お客様を招いて作法にのっとり、お茶でもてなす会を茶道では「茶会」と呼びます。茶会では亭主がテーマを定め、そのコンセプトをもとに、茶碗やお軸、茶器、お花、香り、お菓子、空間のしつらえまでトータルに決めていきます。釜の湯が沸く音、炭のパチパチとはぜる音、畳の上をすり足で歩く音。お客さまが茶碗を手に取ったときに感じる温もりや質感、抹茶の味わいや香り。視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚の五感すべてにアプローチし、空間と時間を設計する。つまり、空間そのものを一種のメディアとしてプロデュースし、五感を通して体験として演出するのが、茶道における茶会です。
正式な茶会になると、実は4時間にも及ぶことがあります。長時間の正座は身体的に大変ですが、その時間は単にお茶を飲む行為をはるかに超えています。
まずはお湯を沸かすところからはじまり、お料理、濃茶、薄茶をいただくのですが、お茶会には決まった大きな流れというものがあります。どこから入って、どのように手を洗うか、お軸を見るのか、どこで亭主とご挨拶をするのか、そういった決まりに沿って亭主とお客様が動き合わせていくことになるので、即興性のある演劇のような要素もあるのですが、このプロセス全体が茶会の本質です。
今日は会場にクリエイターのみなさんがいらっしゃいますが、私は、茶会という営みそのものが、実はクリエイティブディレクションと非常に似ているのではないかと考えています。
茶人は限られた手段の中で、テーマを軸に空間、道具、所作、香りや音までを統合し、五感に響く一つの完成された体験を生み出します。そこには必要なものだけを厳選する削ぎ落とす美学もありますし、制約があるからこそ、自由な発想が生まれるのだと感じます。
一見、型やルールは自由な創造の妨げのように見えますが、その枠の中でいかに工夫するかが創造力を引き出すのではないでしょうか。
さらに、お茶会で実際にお客様を招いた場面では、所作として決まった動きがあったとしても必ず即興性が生まれます。このような型や制約と即興が共存することは、茶道だけでなく、デザインやアートなどクリエイティブの現場においても重要な要素なのではないかと感じています。このように考えると、茶人は現代のクリエイティブディレクターの仕事の原型とも言えるかもしれません。
「守・破・離」に学ぶ創造のプロセス
「守・破・離(しゅはり)」という言葉をご存じでしょうか。物事の習得や革新を三段階に分けた日本独自の概念で、茶道でもその考え方が今も息づいています。
最初は「守」。型を徹底的に学ぶステージです。私自身、3年間裏千家の専門学校で寮に入って修行をしました。掃除、座禅、点前(たてまえ)など、すべて決められたルールを反復し身体に染み込ませました。この段階では創造性よりも素直に型を習得することが第一となります。次に「破」の段階では、型を続ける中で「こうした方が心地いいかも」と感じ、少しずつ工夫を試すようになります。試しながら自分らしさが見えてくるのが「破」です。そして「離」では、型やルールにとらわれず、自分だけの世界観を確立していく段階です。この「離」に至ったからといって終わりではなく、また新しい型を見つけ「守」に戻っていくという循環が大切だと私は思っています。
「型があるからこそ自由になれる。」はじめから自由にやろうとせず、まずは既存のフォーマットの中から学ぶことで、次に活きる発想が生まれ、飛躍できると私自身も実感しています。
どんな文化とも、茶会は成立する
昨今、AIが発達し、あらゆる分野が大きく変化してきています。そのような時代の中で、茶道の形式美は一見、AIでも再現可能に見えるかもしれません。事実として、基本の点前や所作だけをトレースするのであれば、学習させることは十分に可能でしょう。しかし、重要なのは、人と人との間に生まれる偶然性や一瞬の美しさに気づけることではないかと私は思っています。
例えば、どんな茶会も一期一会で、二度と同じ茶会が行われることはありません。同じ道具、同じ季節でも、集まる人が違えば、場の温度や空気感、流れる時間の感覚さえも変わる。亭主からの一方通行ではなく、参加者とつくり上げるライブパフォーマンスなんです。
これまで私は、音楽イベントの中で茶会を開いたり、ビーチでの茶会、メディアアーティストと組んで宇宙をテーマにした茶室、さらには舞踏やヒューマンビートボックス、視覚障がい者との真っ暗闇の茶会など、多様な挑戦をしてきました。




どの茶会も参加者の反応は想像を超えていて、新鮮な気付きを得ることができました。型があるからこそ、どんな相手とでもコラボレーションしやすい。私が今まで様々な茶会をやってきた中で得た大きな発見は、どんな文化と交わっても茶会は成立することが多いということです。そしてそれらはすべて、AIには計算できない「人間の感性」によってこそ導かれているように思います。
茶道は、現代社会のマインドフルネス。時代の中で進化するクリエイティブな伝統
現代では、どんな方でもいろいろな手法で様々な情報にアクセスすることができます。多くの情報の中で過密で多忙な毎日を送っていることでしょう。そんな環境だからこそ、私は「茶会」というフロー体験の力に注目していただければと思っています。
私はお手前をしている時、自分の呼吸が整い、頭が静まり返っていく感覚があります。茶会の間、スマホは見られません。目の前のお茶碗に集中し、味わい、香りを楽しみ、手触りを感じ取る。そうした一連の感覚が、まさに現代版のマインドフルネスなのではないかと感じています。瞑想、サウナ、キャンプなどと同じく、茶室もまた、私たちの心と身体をリセットしてくれる非日常の空間です。
たとえばある子供が、初めて茶室に入った時に「森の中にいるみたい」と言ったそうです。紙、木、土で構成されたその空間が、自然と共鳴する五感を刺激したのだと思います。現代人が忘れかけている感性を思い出させる装置としても、茶道は機能しているように思うのです。
また、茶会をやると、その人のことがよく分かります。どんな器を選ぶか、どんなお菓子を添えるか、どんな空間を演出するか、それらすべてがその人らしさを表しています。好きな音楽や映画、感性の趣向がまるで無言のプレゼンテーションのように、目の前の茶会に表れてくる。そこに共感したり、違和感を覚えたり、あるいは感動したりする。そんな時間の中で、相手のことを知り、自分のことも知ってもらえる。それが茶会なんです。
コーヒーでも紅茶でも構いません。まずは、自分らしいお茶の時間を誰かと共有してみてください。そこには、私たちが忘れがちな感情や、まだ知らなかった相手の表情が、きっと見えてくるはずです。
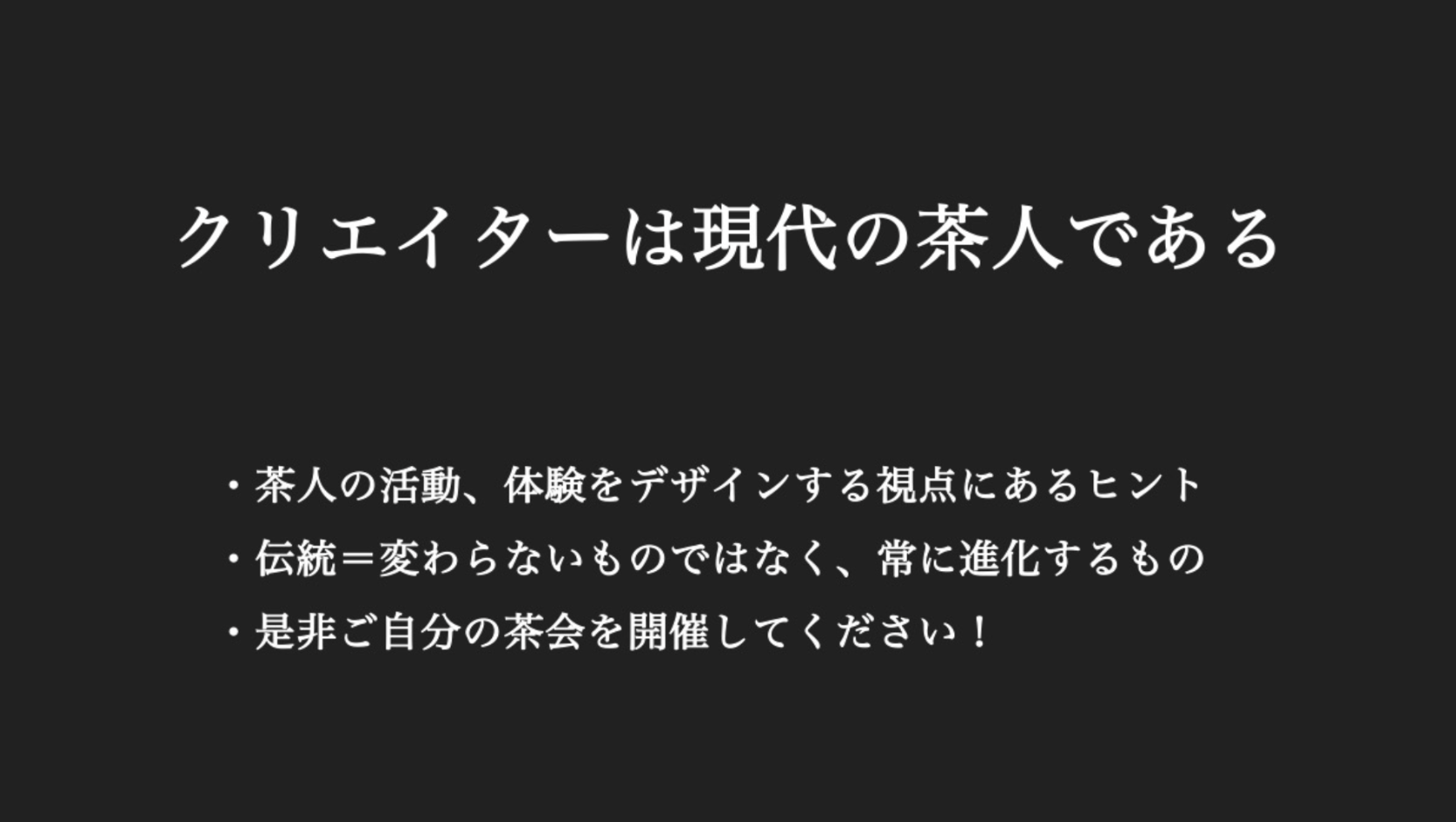
こうして私が茶道を通じてさまざまな人や文化に出会うたびに改めて感じるのは、伝統とは「変わらないこと」ではなく、「変わりながら残ること」なのかもしれない、ということです。伝統を深く尊重しながらも、新しい解釈や表現を柔軟に受け入れる姿勢を持ち、変化してきたからこそ続いているものだと私は思っています。
茶道の本質は、単なる伝統の継承ではなく、人間性の深い探求にあります。400年前の人々と現代を生きる私たちが、同じ美意識や感情で通じ合えることに、茶道の真の魅力があります。
これからも、茶道の伝統を残し、続けるために、茶道という文化と時代の変化を組み合わせて表現を続けることで、多くの人の心に響く体験を届けていきたいと思っています。

■お問い合わせはこちら
株式会社サイバーエージェント インターネット広告事業本部 広報
mail:honbu_pub@cyberagent.co.jp
■インターネット広告に関するご相談はこちら
インターネット広告・デジタルマーケティング全般、リテール領域等
https://www.cyberagent.co.jp/form/id=4
DX領域 (DX全般、戦略策定・UIUXデザイン・開発等)
https://www.cyberagent.co.jp/form/id=268


